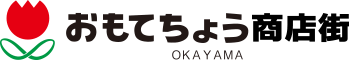表町の歴史
表町の歴史
江戸時代
岡山市の都市としての歴史は、戦国時代も末期の天正元年(1573年)に、宇喜多直家がこの地に本拠を移し、岡山城と城下町の建設を進めたことに始まる。
ただ、この時期はまだ世情も不安定で、直家も合戦に明け暮れていたため、城下町建設はそれほど進まなかったようである。
直家の後を継いだ宇喜多秀家は、豊臣秀吉の信任篤く、備前・美作国に備中の一部を加えた57万4千石の大大名となり、本格的な城下町建設に乗り出す。
まず、慶長2年(1597年)城下町のシンボルとなる岡山城天守閣を完成させ、これと並行して、岡山の北を通っていた山陽道を城下町の中を通るように移し、また備前国内から多くの商人・職人を召し集めて、城下町に住まわせた。
このとき城下町内の山陽道沿いに形成された商人町が、現在の表町商店街である。
現在は住所名からはなくなったが、今も商店街名として残る「上之町(当時は福岡上之町)」や「紙屋町」、「西大寺町」などの町々もこの頃に成立を見たようである。
下之町と紙屋町には、参勤交代の大名が宿泊する本陣が置かれた。
また、岡山と各地を結ぶ主要な道路(往来)はすべて栄町の千阿弥橋(栄町と紙屋町を結ぶ橋)を起点に発していて、まさにこの地は岡山の中心地であった。
その後、岡山藩主は小早川氏、池田氏と変わり、岡山城下町は藩の政治・経済・文化の中心地として栄えた。
18世紀初頭の資料によると、武士を除く城下町住人のうちおよそ半数が商人で占められていた。
明治時代
明治維新の変革により、岡山藩は岡山県となり、岡山城下町には区制が布かれて岡山区となった。
明治22年(1889)6月1日の市制施行により、「岡山市」が誕生し、当時の市域面積は5.77平方キロメートル、人口は47,564人。
市役所は東中山下(現在の深柢小学校)に置かれた。
この頃の資料(明治17年)によると、当時岡山市の商店数は3,487店で、うちおよそ9割(3,150店)が小売商・雑商で、卸売商はわずか6.5%(226店)であった。
また、公共交通が未発達だったため、商店街の商圏は市域を超えた郡部までは及んでいなかったようである。
販売していた商品は、菓子・酒類・八百屋物などの飲食料品のほか、薪炭・履物などで、江戸時代とそれほど変化はなく、「文明開化」の波も、まだ岡山までは到達していなかったことが窺われる。
市制施行の2年後、明治24年(1891)3月、山陽鉄道三石―岡山間が開業。
他のほとんどの都市がそうであったように、岡山市においても鉄道路線は市街地を大きく迂回し、岡山駅は街外れの伊島村との境辺りに置かれた。
この革命的な交通・輸送手段の登場は市の商業にも大きな影響を及ぼし、まず駅の開業により、駅周辺に旅館が建ち始めたため、城下町の西端であった西川を越えて、次第に市街地が西へ拡大して行った。
そして船運の衰退により、旭川河岸の橋本町(現:京橋町)は勢いを失い、代わって鉄道に近い上・中・下之町が賑わいを見せ始める。
その後、鉄道は岡山を起点として津山・宇野・総社・米子方面へ延び、また明治45年(1912)に岡山電気軌道(路面電車)が開通したことにより、商店街の商圏は一気に広がりを見せていった。
「表八ヵ町」といえば、今では上・中・下之町に、栄町、紙屋町、西大寺町、新西大寺町、そして千日前のことを指し、この名称が登場した時は、千日前ではなく、橋本町が加わっていた。
これは、陸上交通が未発達な当時は、維新前と変わらず船が大量輸送手段となっていたため、物資の集積地として、旭川河岸の京橋一帯がたいへん賑わっていたためである。
この「表八ヵ町」なる名称が命名されたのは明治36年(1903)のことで、そのころ上方で流行していた大売出しを岡山でもやってみようと八つの町で結成された「振商会」―今でいう表町商店街連盟―が、八つの町の総称ということで名付けたのがこの名称であった。
このとき行われた大売出しでは、銀時計や金の指輪などの豪華景品も用意され、大成功を収めたが、景品を見ると、
岡山にもようやく洋装品がお目見えしていたことが分かる。この大売出しに先立つこと7年、明治29年(1896)、栄町で「誓文払い」が始められていましたが、このときから表八ヵ町合同で行われることになった。
今や岡山の秋の風物詩となった「備前岡山ええじゃないか 大誓文払い」はこうして誕生した。
大正・昭和戦前
表町の最南部にある千日前商店街は、江戸時代は天瀬可真町と呼ばれ、侍屋敷が立ち並んでいた。
明治になると料理屋などに使われていたが、橋本町に近い割には基本的には淋しいところであった。
この地区に変化をもたらしたのは、映画館の立地である。
まず明治45年(1912)1月に帝国館(現:岡山松竹)が先陣を切り、大正8年(1919)に金馬館、同15年(1926)に若玉館(旧テアトル岡山)、昭和13年(1938)に文化ニュース劇場(現:SY松竹文化)が次々に開館する。
それに伴い、飲食店も軒を連ねるようになり、人影まばらだった天瀬可真町は岡山一の娯楽街へと大変身を遂げた。
このため町の名も、大阪の繁華街の名をとって、このころから「千日前」と呼ばれるようになった。
ちなみに千日前が橋本町に変わって表八ヵ町に加わるのは戦後のことである。
明治から大正と時代を経るにつれ、小売商のスタイルも徐々に現代のものに近づいてゆく。
江戸時代からの、あまり商品を陳列せず、店頭に座ったまま接客する形から、次第に商品を展示装飾し、商品には値札を付け、店員も立って接客という形へと変化していく。
このような販売スタイルの変化は、新しい小売業の業態をも生み出していくのである。
大正8年(1919)に設けられた公設市場もそのひとつで、もともとこれは、大正7年に全国的に発生した米騒動を受けて、
市民の生活不安を和らげるため、日常生活必需品を安く販売することを目的に設置されたものである。
その後は私設の市場も設けられ、昭和8年(1933)には11ヶ所にまで増えました。現在に例えれば、スーパーマーケットのはしりといったところであろうか。
公設市場は戦後も設けられ、物不足の時代に市民の生活を支えつづけるが、スーパーの登場により徐々に減少、平成元年(1989)6月、清輝公設市場の廃止によりその役割を終えた。
さらに、この頃岡山に登場した新業態は百貨店で、その代表的存在は、今も表町に店舗を構える天満屋である。
西大寺に興った天満屋は、小間物商から呉服商へと成長し、大正元年(1912)に中之町へ支店を設け、岡山進出の第一歩を踏み出した。
その後、下之町支店開店、岡山店の本店化を行い、大正14年(1925)3月、下之町に木造3階建ての店舗を開設する。
この店舗は呉服から洋服・文具・化粧品など様々な商品を扱う店舗で、「百貨店」天満屋はこのときに成立したとみることができる。
昭和11年(1936)には、当時西日本随一と言われた鉄筋コンクリート地下1階・地上6階の新店舗を完成させ、名実ともに岡山を代表する百貨店へと成長した。
昭和12年(1937)日中全面戦争が開始すると、商業者の中にも召集されるものが相次ぎ、また商業から軍需産業への労働者の移動も増えたため、商業従事者が減少していく。
続いて生活必需品が不足し始め、商品そのものが店頭から徐々に姿を消していった。
さらには営業の規制、奢侈品の規制、配給制度などの経済に対する国の統制が強化されると、商業活動も次第に停滞していく。
昭和16年(1941)の対米英開戦はこの状況に拍車をかけ、市の商業はまさに瀕死の状況に追い込まれた。
そして昭和20年(1945)6月29日未明、岡山市は米軍B29による大空襲にみまわれ、開府以来370年にわたって連綿と築かれてきた城下町は、わずか一晩のうちに廃墟と化してしまったのである。
昭和20・30年代
空襲によりすべてを失った岡山市の商店街ですが、たくましく復興していく。
復興の始まりはヤミ市。
当時、ヤミ市は市内あちこちに開かれていて、最も規模が大きかったのは駅前中筋のものである。
幅4メートル、長さ350メートルの通り沿いに、露店やバラック建ての店がびっしり並び、食料品・衣料品はじめ日用品などのヤミ物資を売っていた。
駅前地区は、岡山駅の開業により形成された比較的新しい市街地で、旅館や食堂が数多く立地していたが、「商店街」と呼べるほどの小売店の集積はなかった。
このヤミ市の開設により、駅前地区は有力な商業地区として、新たな第一歩を踏み出した。
奉還町商店街も、県庁が天神町(現:県立美術館)から上伊福(現:岡山工業高校)に移転したことにより、岡山駅―県庁を結ぶルートとしてヤミ市が開かれ、徐々に立ち直りを見せていった。
一方、表町においても、昭和20年(1945)10月10日、天満屋がいち早く営業を再開、その3日後には「岡山市中央商店街復興委員会」が結成され、街を挙げて商店街の復興に取り組んだ。その結果、翌21年11月には、恒例の大誓文払いを行うまでに回復していった。
復興が軌道に乗ると、各商店街は更なる発展のため、施設の更新に乗り出す。
昭和24年(1949)12月に天満屋バスステーションが完成すると、表町は駅前に変わり再び岡山の商業の中心地に返り咲く。
アーケードの整備も進められ、昭和32年(1957)3月の上之町を最後に、表八ヵ町全体のアーケードが完成する。
同じ年には県庁が下伊福から現在地に移転、下之町周辺の中心性はますます高まる。
昭和40〜60年代
昭和47年(1972)3月15日、山陽新幹線の新大阪―岡山間が開通した。
山陽鉄道の開通から81年後に迎えたこの第二の交通革命は、岡山市の商業にかつてない変化をもたらした。
国体開催にともなう整備事業により、市の表玄関としての体裁を整えていた駅前地区であるが、こと、商業面に関しては、中筋の商店街に加え、岡山会館、ダイエー駅前店があるのみで、しかも岡山会館・ダイエーとも商業専門ビルではなく、表町に比べると、集客力の点ではかなり劣っていた。
しかし、新幹線の開通により駅前地区は空前の出店ラッシュにみまわれる。
開通翌年5月の、県外百貨店第1号の髙島屋岡山店の出店が口火を切り、続いてその翌年には西日本有数の規模を誇る地下街「岡山一番街」がオープン、さらにその翌年2月には岡山ターミナルビルが完成し、そごうが出店するなど、3年連続で大型店が出店する。
出店はこれでも止まらず、昭和53年(1978)11月にダイエー・ドレミの街、翌年5月にニチイ岡山店(現:ビブレ)、6月にビブレ岡山が立て続けにオープン。
これにより、駅前地区は表町と肩を並べる商業地区に急成長を遂げる。
商業環境の激変は、駅前地区に止まらず、天満屋は、新幹線開通に先立つ昭和44年(1969)9月、店舗北側へ増築し、
店舗面積を一気に倍増させてオープン、同時にバスステーションの整備も行った。
(これが現在の店舗)先に記したように、同年にはイズミとユニードも表町へ出店し、さらに開通翌年の48年11月には中之町地下街が、その翌年11月には長崎屋岡山店(現:ファンク岡山)がオープンし、表町地区の集客力も飛躍的に向上した。
こうした新幹線開通をはさんだ一連の出店ラッシュにより、表町が絶対的な力を誇っていた岡山市の商業は、ここに、表町・駅前に二大商業核を擁する二極化時代を迎える。
周辺1市7町3村との合併を終えた昭和50年、岡山市の人口は50万人を超えていたが、中心部の人口は昭和40年代に入ってからは逆に減少を続けていた。
人口の郊外移転―郊外の宅地化が急速に進んでいたのである。
同時に自動車の普及も進み、市民の買物スタイルは大きく変わりつつあった。
この変化に機敏に対応していったのが、昭和30年代に登場したスーパーマーケットである。
昭和30~40年代のスーパーは、まだ都心部へ出店していたが、昭和50年代に入ると、広大な駐車場が準備できる郊外へと出店の眼は移る。
その本格的第1号となったのが、昭和51年(1976)12月のジャスコ岡山店の青江への出店である。
その後、天満屋が設立した天満屋ストア(ハピータウン)や、新たに流通業に参入した中鉄商事・両備バスなどの地元企業に加え、イズミ・イズミヤなどの県外企業も次々と郊外に出店する。
この結果、新幹線開通直後の昭和49年(1974)におよそ136,000平方メートルだった大型店の面積は、昭和63年(1988)には275,000平方メートルと倍増し、市内の小売店面積のほぼ半分を占めるほどになった。
こうした商業環境の激変のなかで、岡山市と商店街は有効な対抗策を講じる必要に迫られる。
岡山市は、岡山商工会議所とともに、国の制度を活用して、昭和45年(1970)、同50年(1975)、同60年(1985)の
3度に渡り商業近代化計画を策定する。
駅前地区は、新幹線の開通により自然と開発が進んでいったため、特に50年と60年の計画は、表町地区に的を絞って作成された。
岡山シンフォニービルや、オランダ東通りの構想は、このときに生まれたものである。
この流れを受けて、表町商店街でも、施設のリニューアルや、近代化計画を実現するための組織が結成されていく。
昭和53年(1978)7月には新アーケード(中之町~栄町間)とカラー舗装(中之町~新西大寺町)が完成するが、これが現在のアーケード・カラー舗装である。
昭和61年(1986)には前年に策定された近代化計画を受けて、「表町商店街活性化モデル事業」をまとめ、「オランダ」や「サーカス」をテーマとして商店街を活性化していく方針を打ち出した。
平成時代
昭和末期から平成初期にかけては、
いわゆる「バブル景気」と呼ばれる未曾有の好景気に沸いた時期だったが、その割には大型店の出店は増えていない。
「大規模小売店舗法」(大店法:昭和49年3月施行)が大型店の出店を厳しく規制していたためである。
しかし、規制緩和の流れの中で、大店法は平成2・4・6年の3度に渡り法律や運用の改正が行われ、徐々に出店がしやすくなっていきく。
そうなると、大型店は、今までにないペースでその数を増やしていくのである。
平成3年(1991)に103店、およそ304,000平方メートルだった市内の大型店は、8年後の平成11年(1999)には183店、524,000平方メートルにまで急増した。
この間、特徴的なことは、増加した店舗の96%が郊外への出店だったこと、そして、業態も今までのスーパーやホームセンターに加え、家電や紳士服、ドラッグストアなどの専門店、あるいはこれらの店舗が複数組み合わさったショッピングセンター形式の出店が増えてきたことが挙げられる。
大店法は平成12年(2000)5月をもって廃止となり、6月からは別の観点から規制を行う「大規模小売店舗立地法」が施行された。
このような急激な郊外店増加は、都心の商業へも大きな影響を与え、都心にあるスーパーは次々に業態を変換し、専門店となっていく。
ニチイは昭和63年(1998)に全館の専門店(ビブレ)化を完了、長崎屋は昭和60年(1985)に撤退していったが、
そのあと、平成元年(1889)にウオッチマンが入店、イズミも同年ファッション専門店・fitz(現:ロッツ)となる。
フジビルのダイエー駅前店も、昭和60年、平成6年(1994)の2度の大改装を行って専門店化し、「岡山OPA」となった。
また、新業態が着々とその勢力を伸ばしていく。
今や現代人の生活に欠かせない存在となったコンビニエンスストアの登場である。
昭和56年(1981)12月、ローソンのオープンがその第1号であるが、その後、サークルK、ファミリーマート、ヤマザキデイリーストアなど、業界大手が次々と進出、最大手のセブン・イレブンも平成9年(1997)4月に市内へ初出店、サンクスも翌年2月に市内1号店をオープンさせた。
現在、市内のコンビニ数は200店を越えている。
90年代は大型店やコンビニが大幅に増加したため、市内小売業の従業者数や年間販売額、売場面積は数値を伸ばしたが、
商店数は昭和63年(1988)の7,900店をピークに減少に転じる。
大型店の増加や、いわゆる「バブル崩壊」後の消費不況の影響により、既存の中小店舗の廃業が増加していったためである。
この波は当然のように都心商店街にも押し寄せ、後継者不足や空き店舗の増加という形で現れる。
また、商店街の通行量も年々減少し、一刻も早い建て直しが急務の課題となった。
平成3年(1991)の上之町のリニューアルがその先駆けとなる。
上之町はアーケード・カラー舗装の一新を行うと同時に
店舗のリニューアルも実施、また再開発事業により、商店街の北端に岡山シンフォニービルと城下地下駐車場も同時期に完成した。
効果はてき面に現れ、上之町の通行量はほぼ最盛期のレベルにまで回復する。
都心商店街の衰退に加え、人口のドーナツ化現象、事業所の郊外移転により、都心全体に活力がなくなっていくという状況―全国的に、特に中小都市において
顕著となったこの問題に対処するため、平成10年(1998)に国が11省庁合同で「中心市街地活性化事業」を始める。
岡山市は同年、この制度を利用して「岡山市中心市街地活性化基本計画」を策定、商業の活性化に合わせて、都心への定住化の促進、交通体系の見直しなど、様々な観点から都心の活性化に取り組むこととなった。
こうした状況を反映して、都心へのひさびさの大型店出店は歓迎ムードで迎えられる。
平成10年(1998)11月のイトーヨーカ堂、翌年3月のクレド岡山の開店である。
都心への10,000平方メートルを越える出店は、ビブレ以来およそ20年ぶりということもあって、市民の期待は大きく、
開店日には大変な賑わいを見せた。
さらに平成12年(2000)11月にはフィッツが全面改装を行い、
人気の都市型雑貨店・ロフトを中心とした専門店ビル・ロッツへ衣替えし、
都心の集客力はさらに高まった。